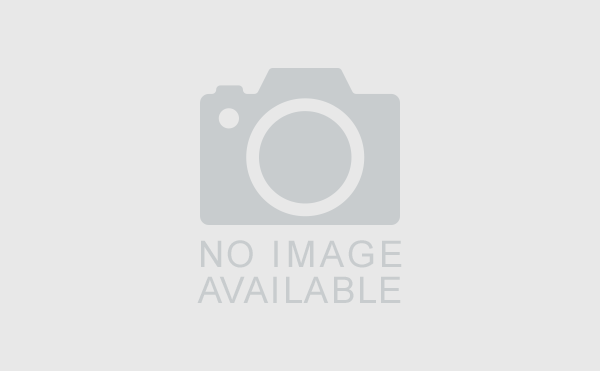【仮説と検証】香川県中3生診断テスト第2回の成績最大化
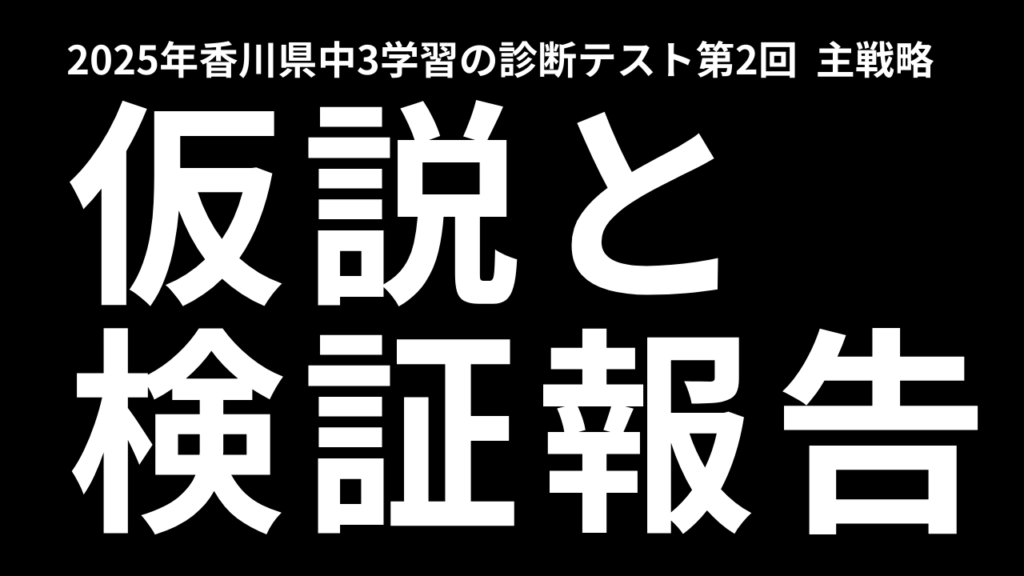
2025年度第2回香川県中学3年生診断テストにおいて、岡川塾の塾生平均点は第1回から7.9点の上昇を果たしました。今回の診断は県内全体で「難化した」と評されているにもかかわらず、成績を伸ばすことができた点は大きな成果であり、保護者の皆様にとっても安心材料になったことと思います。
この成果の背景には、生徒一人ひとりの努力はもちろんですが、それを確実に成果につなげるためのプロ講師による戦略的な指導がありました。私たち岡川塾では、昨年度も中3生の平均点を約30点押し上げた実績を持ち、その経験を活かして今年度も「仮説と検証」を繰り返しながら指導法を磨いてきました。以下では、その具体的な取り組みと検証結果を整理してご紹介します。
仮説1:過去問を5年分、全問仕上げる
検証結果:確実に点数は上がるが、厳格な採点が不可欠。
受験対策において「過去問演習」は定番ですが、その取り組み方に大きな差が出ます。私たちが掲げた仮説は「過去5年分をすべて仕上げる」というもの。特に診断テストでは数年ごとに似た論点や形式が繰り返し出題されるため、1年分の演習では偏りが大きく、得点力向上には十分ではありません。
また、ここで重要なのは「採点の厳格さ」です。生徒自身による自己採点はどうしても甘くなりがちで、誤答を誤答と認識できずに通り過ぎてしまうリスクがあります。岡川塾では講師が正確かつ手厳しく採点し、わずかな表現のズレや論点の見落としも指摘。これにより「正しく解ける」状態まで鍛え上げることが可能となりました。
仮説2:頻出難問を複数回の試験で定着度を確認
検証結果:意識改革を促進。弱点放置を徹底的に防止。
診断テストには「頻出難問」と呼ばれる問題があります。正答率は低いものの、毎年のように出題されるため、得点差が大きく開くポイントです。私たちはこれらの問題を複数回にわたって追試形式で出題し、定着率を確認しました。
解けなかった場合は「復習不足」であることが事実として明らかになります。単に講師が指摘するよりも、生徒自身がデータを通じて自覚することは意識改革に直結します。「まだ自分は覚えていない」「練習が足りない」と自分で理解できるため、次に向けた行動につながるのです。
特に重要なのは、できない生徒をそのままにしないこと。弱点が放置されると全体の底上げは望めません。岡川塾では「解けない生徒の割合を最小化する」ことを徹底し、クラス全体の学力を押し上げています。
仮説3:理社の記述問題5年分+不規則動詞60単語の暗記
検証結果:英語は大成功、理社は傾向変化の影響で限定的。
英語における不規則動詞の暗記は、夏までに仕上げることが必須です。ここで完成させれば、第2回以降の診断におけるスペルミスをほぼ防げます。事実、今回のテストでもその効果が明確に現れました。
一方で理科・社会については、近年の出題傾向が変化しました。以前は「教科書の表現をそのまま書けるか」が問われていましたが、今回は「自分の言葉で説明する」自由度の高い記述問題が増加。その結果、学校ごとの採点基準による得点の差が大きく、演習効果が限定的となりました。
ただし、この変化を早い段階で把握できたこと自体が次の対策に役立ちます。記述対策を「暗記」から「思考力型」へシフトさせる必要性を生徒に伝え、今後の勉強方針を修正できた点は大きな収穫でした。
仮説4:国語作文と英語英作文の出題的中
検証結果:戦略的準備が的中。安定的な得点源を確保。
作文は点差がつきやすい領域ですが、出題傾向には一定のパターンがあります。岡川塾では過去の出題データを徹底分析し、3〜4年ごとに切り替わるパターンを予測。今年は前年型の「Aパターン」と3〜4年前の「Bパターン」の双方に対応できる形で準備を進めました。
結果は見事に的中。本番では事前に練習した「書き方の型」を使ってスムーズに作文が完成しました。細かい表現のミスによる部分点減点はあったものの、国語作文で最大8点、英作文で4点、合計12点を安定的に確保できました。
診断テストの採点基準は「書けば減点されにくい」仕組みになっているため、答案を空欄にしない姿勢こそ重要です。時間が足りない状況でも「型」があることであきらめずに書き切ることができ、大きな武器となりました。
成果と今後への展望
今回の第2回診断テストでは、難化した状況の中でも塾生平均点が7.9点上昇しました。これは単なる偶然ではなく、仮説を立て、実際に検証し、その結果を分析して次の戦略へ反映する「成績最大化サイクル」の成果です。
もちろん、勉強は生徒自身の努力なしには成り立ちません。しかし、その努力を「結果につながる努力」に変えるためには、指導者側の戦略が欠かせません。今回の取り組みを通じて、岡川塾が大切にしているのは次の3点です。
- 徹底的な演習量と正確な採点
- 弱点を放置しない追試・再確認の仕組み
- 傾向変化を素早く捉えた柔軟な対策
これらを継続的に実行することで、生徒たちの成績を一歩一歩引き上げていきます。
次回の第3回診断テスト、そして本番の入試に向けて、私たちはさらに指導をブラッシュアップし、塾生全員が確実に成果を出せるよう全力を尽くしてまいります。